
仮想通貨でちょっと利益が出たけど、20万円以下だったし、税金ってどうなるの?
暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益が少額だった場合、「申告しなくてもいいの?」と気になりますよね。特に副業ブームの今、ちょこっと投資してみたという方も増えています。
実は、給与所得がある人であれば、暗号資産などの所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要とされています。
――でも、ちょっと待ってください。
副業をしていたり、年収が高かったり、給与が複数から出ている場合は話が変わってくるんです。
さらに、確定申告は不要でも「住民税の申告が必要になるケース」もあるので、注意が必要なんです。
この記事では、暗号資産で得た利益が20万円以下の場合の「税金ルール」を、かんたん&わかりやすく解説します。
自分が申告対象かどうかをしっかりチェックして、安心して仮想通貨ライフを楽しみましょう!
暗号資産の「税金ルール」とは? 基本をおさらい


暗号資産を取引して得た利益には、しっかりと税金がかかります。
売却や交換、マイニングなどの取引によって得た収入は「雑所得」に分類され、税金の対象になります。



仮想通貨は「雑所得」として課税されます。
取引内容によって税金の扱いも変わるんだよ。
- 雑所得として課税される仕組み
- 対象となる取引の具体例
暗号資産の利益は他の所得と合算されるため、税率が高くなることもあります。
まずは、どんな利益が課税の対象になるのかを正しく理解しましょう。
それでは、まず「雑所得」とは何かを見ていきましょう。
「雑所得」として課税される仕組み
暗号資産で得た利益は、原則として「雑所得」に区分されます。
雑所得は、給与所得や事業所得などとは別に、総合課税の対象となる所得です。
つまり、他の所得と合算されて、合計額に応じた税率が適用されます。
この税率は5%〜45%と段階的に上がる「累進課税方式」が使われます。
- 暗号資産の利益は「雑所得」
- 総合課税で税率が変わる
- 所得が多いほど税率も高くなる
たとえば会社員として給与を得ながら、仮想通貨でも利益を出した場合、両方の所得が合算されます。
その合計金額に応じて、所得税や住民税が決まる仕組みです。
このように、暗号資産は副業感覚で始められる一方で、税務面では見落としがちなポイントが多く存在します。
自分の所得がどのくらいになるのかを、日頃から確認しておくと安心です。
雑所得の考え方がわかったところで、どんな取引が対象になるのかも確認しましょう。
対象となる取引の具体例(売買・交換・決済など)
暗号資産では「売却」や「他の通貨との交換」など、いろいろな取引が課税の対象になります。
代表的なのは、ビットコインなどの仮想通貨を日本円に換金したときです。
また、商品購入やサービスの支払いなどに使った場合も、利益が確定したとみなされます。
さらには、マイニングやエアドロップなど、通貨を得た場合も課税対象です。
- 暗号資産を売却したとき
- 他の通貨と交換したとき
- 商品やサービスを購入したとき
- マイニングや報酬で得たとき
たとえば、ビットコインを100万円で購入し、200万円に値上がりしてから売却したとします。
この場合、差額の100万円が雑所得となり、所得税と住民税の課税対象になります。
さらに、ビットコインを使って買い物をした場合にも、その時点の価格で評価され課税されます。
つまり、現金化していなくても「利益が確定した」とみなされれば、課税されるということです。
こうした取引のルールをしっかり把握しておくことが、トラブルを防ぐ第一歩です。
以上が、暗号資産に関する基本的な税金の考え方です。
次の章では、話題になりやすい「20万円以下なら申告不要?」というルールについて解説します。
20万円以下の利益は「申告不要」って本当?
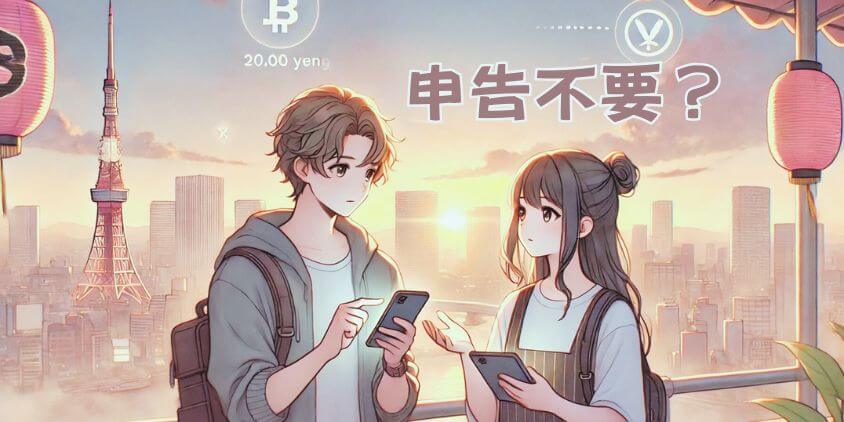
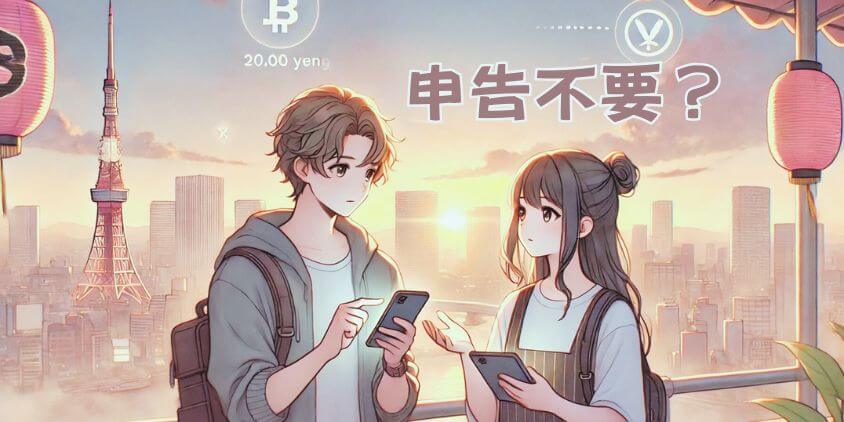
暗号資産の利益が20万円以下なら、確定申告は不要だと聞いたことがあるかもしれません。
たしかに一部の人には当てはまりますが、すべての人に当てはまるルールではありません。



「20万円以下ならOK」と思いがちですが、実は条件つきです。
会社員か個人事業主かでも違うんです。
- 会社員と個人事業主で異なる申告義務
- 「20万円以下=非課税」ではない理由
- 住民税の申告は必要なケースも
この章では、職業別の違いや住民税の扱いなどを、わかりやすく説明します。
まずは、会社員と個人事業主で何が違うのかを見ていきましょう。
「会社員」と「個人事業主」で異なる申告義務
まず、会社員で年末調整を受けている人は、暗号資産の利益が20万円以下なら確定申告は不要です。
この「20万円以下特例」は、年末調整が済んでいる給与所得者だけに認められたルールです。
一方で、個人事業主やフリーランスは、暗号資産の利益が1円でもあれば確定申告が必要です。
これは、日頃から確定申告を行う立場にあるため、20万円以下でも申告義務があるという考え方です。
- 年末調整を受けた会社員は20万円以下でOK
- 個人事業主は1円でも申告が必要
- 複数の給与がある会社員は要注意
たとえば、会社からの給料とは別に仮想通貨で数万円の利益が出たとしても、会社員なら確定申告が不要なケースがあります。
しかし、フリーランスの人が同じ金額の利益を得た場合は、確定申告をしないといけません。
つまり、税金ルールは「立場」によって大きく変わることを知っておく必要があります。
続いて、「非課税ではない」という点も詳しく見ていきましょう。
「20万円以下=非課税」ではない理由
よくある誤解が「20万円以下なら税金はかからない」というものです。
実はこれ、確定申告が不要になるだけで、税金が免除されるわけではありません。
たとえば、住民税の申告は別に必要となるケースがあります。
そのため、利益が20万円以下でも、市町村への申告は必要なこともあるのです。
- 20万円以下でも課税対象になる
- 確定申告が不要なだけ
- 住民税の申告は別途必要
たとえば10万円の利益を得た会社員の場合、確定申告は不要でも、住民税の申告は求められる可能性があります。
この点を見落としていると、あとから市町村から申告漏れを指摘されることもあります。
税務署ではなく自治体の話なので、意外と盲点になりやすいです。
次に、住民税の申告が必要なケースをくわしく見ていきましょう。
「住民税」の申告は必要なケースも
住民税の申告は、原則として確定申告と連動しています。
しかし、確定申告が不要なケースでも、住民税だけは申告しなければならない場合があります。
とくに20万円以下の利益で確定申告を省略した人は、市区町村への申告を忘れないようにしましょう。
自治体によっては、申告しないと後日「申告のお願い」が届くこともあります。
- 確定申告しない場合でも要注意
- 住民税の申告は別ルール
- 市町村によって申告方法が違う
たとえば、仮想通貨で5万円の利益が出ていたとして、確定申告を省略した場合でも、住民税は課税される可能性があります。
その場合、自分から市役所や町役場に申告を行う必要があります。
オンラインで対応できる自治体もありますが、多くは役所の窓口や郵送です。
住民税の申告を忘れると、ペナルティはなくても納付書が届かずトラブルになることもあります。
このように、「申告不要」と思って安心してしまうと、思わぬところでつまずく可能性があります。



20万円以下でも「絶対に大丈夫」ではありません。
住民税や職業によって申告義務があるんです。
暗号資産の「確定申告が必要」なケースとは


暗号資産の利益が出たとき、どんなケースで確定申告が必要になるか気になりますよね。
実は、20万円以下でも申告が必要なことがありますし、副業や他の収入との合算にも注意が必要です。



たとえ少額でも、条件次第で確定申告は必要です。
特に副業や経費の扱いには要注意!
- 副業や複数の収入がある場合の注意点
- 経費を差し引けるのはどんな場合?
- 20万円以下でもバレる?税務調査のリスク
まずは、副業やアルバイトなど、他にも収入がある人が気をつけたいポイントから見ていきましょう。
「副業や複数の収入」がある場合の注意点
仮想通貨の利益だけでなく、副業の収入がある場合は合算して判断されます。
たとえば副業で10万円、仮想通貨で15万円の利益があった場合、合計25万円となり確定申告が必要です。
「それぞれ20万円以下だから大丈夫」と考えてしまうと、申告漏れになってしまいます。
そのため、副業やフリーランスでの収入がある人は、全体の収入を合計して判断しましょう。
- 副業収入と仮想通貨利益は合算
- 合計20万円超で確定申告が必要
- 雑所得全体を確認して判断
たとえば、仮想通貨で5万円、副業で17万円の利益がある場合も、合計22万円となり申告が必要になります。
また、他にもネット収入やポイントサイトなどの雑所得も、すべて合算対象です。
見落とさずにしっかり全体を計算しましょう。
次は、仮想通貨にかかる「経費」について解説します。
「経費を差し引ける」のはどんな場合?
暗号資産の利益を計算するとき、経費として差し引けるものがあります。
代表的なものは「購入時の手数料」「取引時の出金手数料」などです。
また、暗号資産に関する書籍代やセミナー代、取引用の通信費も条件次第で経費になります。
ただし、経費にできるかは「暗号資産の取引に直接関係しているか」がポイントになります。
- 取引所の手数料
- 入出金の際の手数料
- 仮想通貨の勉強代
- 取引に関する通信費
たとえば、ビットコインの売買にかかった出金手数料は経費になります。
また、仮想通貨について学ぶために購入した書籍やオンライン講座も、直接取引のためなら経費になります。
スマホやPCで取引している場合、その通信費の一部も明確に区分できれば経費計上できます。
こうした経費を計上することで、課税される所得を減らせるので、しっかり把握しましょう。
最後に、20万円以下でも油断できない「税務調査」の可能性について解説します。
20万円以下でもバレる? 税務調査のリスク
「20万円以下だから申告しなくてもバレない」と考えるのは危険です。
最近は取引所から税務署への情報提供が進んでおり、取引履歴はチェックされています。
また、SNSやブログなどから収入がある人は、関連性があると判断されて調査対象になりやすいです。
無申告が発覚した場合は「無申告加算税」や「重加算税」といったペナルティの対象にもなります。
- 税務署は情報収集している
- 無申告はペナルティ対象
- 追徴課税で高額になることも
たとえば、取引所から提供された情報をもとに、利益が20万円を超えていることが税務署に知られた場合、調査が入ることもあります。
申告していないことが発覚すると、15%〜40%の加算税が課されることもあります。
さらに、場合によっては延滞税や利息も加わり、納税額が膨れ上がることも。
後から後悔しないためにも、少額でも記録を残し、必要なら申告する意識を持つことが大切です。



20万円以下でも油断は禁物!
税務署は情報を持っているので、記録や管理はしっかりと!
「申告が不要でも」っておきたい3つのこと
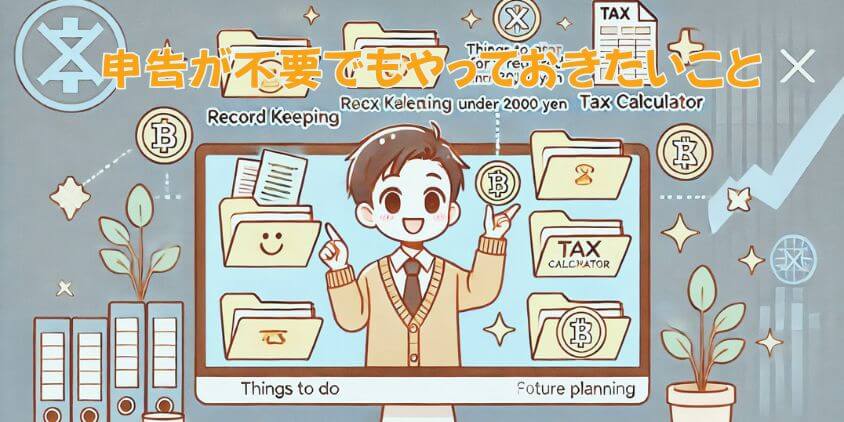
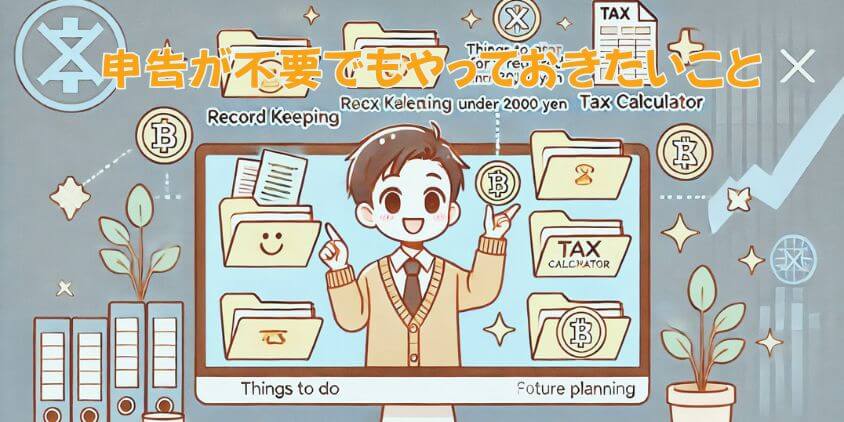
たとえ暗号資産の利益が20万円以下でも、何もしなくてよいわけではありません。
将来的なトラブルを防ぐためにも、最低限やっておくべきことがあります。



申告が不要でも油断しないで!
記録と管理はしっかりしておくと安心です。
- 年間取引履歴を保存しておく
- 税金計算ツールで利益を把握する
- 将来のために記録と対策を習慣化する
では、申告が不要でもやっておきたいことをひとつずつ見ていきましょう。
「年間取引履歴」を保存しておく
まず最も大切なのは、年間の取引履歴を保存しておくことです。
申告が不要な年でも、後から確認や調査が入ったときに備えて記録を残すのはとても重要です。
また、翌年以降に申告が必要になる場合でも、過去の履歴があると損益の通算などがスムーズに行えます。
特に税務署から照会を受けたときに備え、データは最低でも7年間保存しておきましょう。
- 取引所の履歴は定期的に保存
- ExcelやPDFでバックアップ
- 税務調査対策にもなる
たとえば、年末に1回でも仮想通貨を売却した場合、その履歴をPDFやスクリーンショットで保存しておくと安心です。
また、国内外複数の取引所を使っている場合は、すべての履歴をまとめておきましょう。
こうした記録は、もし税務署から問い合わせがあってもスムーズに対応できる材料になります。
「今は申告がいらないから」と記録を残さないのは、将来のリスクになります。
次は、利益の把握に便利なツールについてご紹介します。
「税金計算ツール」で利益を把握する
仮想通貨の損益を正確に把握するには、計算ツールの利用が便利です。
取引が多い人や複数の通貨を持っている人は、手作業ではミスが起こりやすいからです。
たとえば「Gtax」などのサービスを使うと、取引所の履歴を読み込むだけで自動で利益計算ができます。
このようなツールを使うことで、正確な金額を把握でき、必要なときすぐ申告に移れます。
- 利益が出たかすぐわかる
- 税額の試算もできる
- 申告が必要なタイミングを逃さない
たとえば、年間の損益が19万円か20万1000円かでは、申告義務が変わってきます。
このような微妙な差も、ツールを使えば瞬時に確認できます。
さらに、翌年に向けて含み損や節税方法を検討する材料にもなります。
正確な損益をつかんでおくことが、トラブルの回避や節税にもつながるのです。
では、最後に日頃からできる習慣化の工夫をご紹介します。
「将来のために」記録と対策を習慣化する
暗号資産の取引は、急に利益が出ることがあります。
そのため、普段から記録や損益チェックを習慣にしておくことが大切です。
年末になって慌てて計算しないよう、月ごとや四半期ごとに確認すると良いでしょう。
また、税制改正があったときにも対応しやすくなります。
- 毎月損益をチェックする
- 定期的に取引履歴を保存する
- 節税のタイミングを逃さない
たとえば、含み損が大きい年は早めに損失を確定しておくと、翌年の税負担を減らせる可能性があります。
また、ふるさと納税やiDeCoなどを組み合わせると、さらに節税につながります。
税金は年単位での調整が重要なので、計画的な管理がカギになります。
「来年はたくさん利益が出そう」と思うなら、今年中にできる対策を考えてみましょう。
記録と計画が、安心して暗号資産を楽しむための土台になります。



「いま申告が不要」でも、記録と準備が大事です。
来年のために、コツコツ続けておきましょう。
20万円以下でも「油断せず」税金ルールを把握しよう
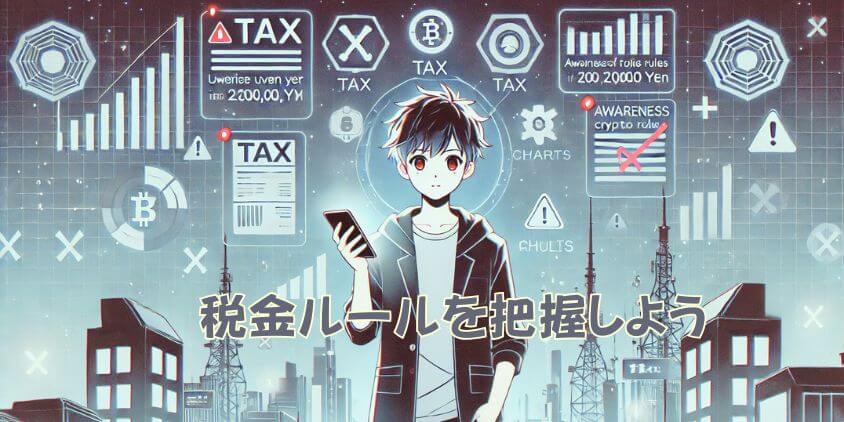
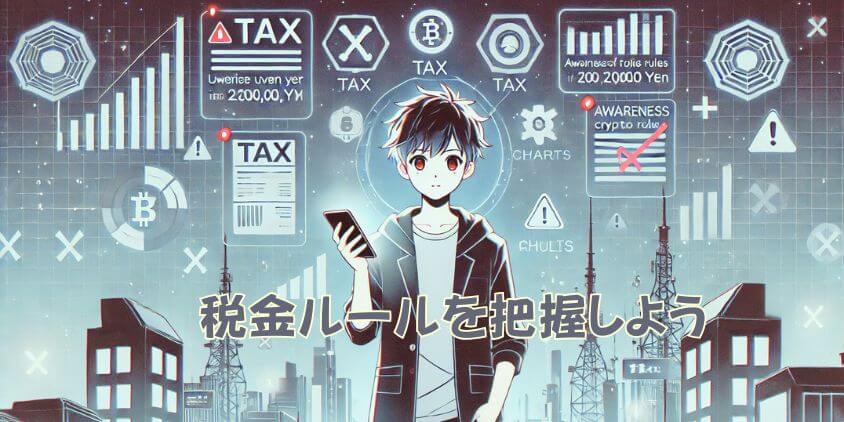
暗号資産の利益が20万円以下だからといって、安心していいとは限りません。
立場や他の収入状況によっては、確定申告や住民税の申告が必要な場合もあります。



「20万円以下だから大丈夫」と思い込むのは危険です。
ルールを知って正しく判断しましょう。
- 20万円以下でも申告が必要な場合がある
- 住民税の申告は忘れずに行う
- 正確な記録と損益計算を習慣化する
税金のルールは毎年変わる可能性もあるため、最新情報を確認しながら対応していくことが大切です。
不安なときは、仮想通貨に詳しい税理士などの専門家に相談するのもおすすめです。
自分の利益額や立場に合った申告判断ができるよう、日ごろから損益と記録をしっかり管理しておきましょう。
税金の不安を減らせば、安心して投資に取り組めます。
「今年は関係なかったから大丈夫」と思わず、将来のために準備しておくことが大切です。



利益が少なくても、税金の知識があると安心!
備えておくことで、あとから困りませんよ。
Q&A:暗号資産の税金
暗号資産の利益が20万円以下なら申告しなくていいの?
会社員で年末調整を受けている場合、暗号資産の利益が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、フリーランスや個人事業主は1円でも申告が必要です。また、確定申告は不要でも「住民税の申告」は別途必要なケースがあるので注意しましょう。
20万円以下の利益でも住民税の申告は必要?
はい、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要なことがあります。自治体によってルールが異なるため、住んでいる市区町村のホームページなどで確認し、必要に応じて申告を行いましょう。
副業と暗号資産の利益は合算して考えるの?
はい、副業などの雑所得と暗号資産の利益は合算されます。たとえば、副業収入が10万円、仮想通貨で15万円の利益がある場合は、合計25万円となり確定申告が必要です。「それぞれが20万円以下」でも合計で判断する必要があります。
仮想通貨の取引で経費として認められるものは?
購入時や売却時の手数料、取引所の出金手数料、仮想通貨に関する書籍・セミナー代、取引用の通信費などが該当します。ただし、取引に直接関係していることが条件です。経費を差し引くことで課税対象額を減らすことができます。
20万円以下でも税務署にバレることはあるの?
あります。仮想通貨取引所は税務署に取引情報を提供しているため、取引内容は把握されています。無申告が発覚すると、加算税や延滞税などのペナルティを受けることもあるので、正しい記録と管理が大切です。
申告不要でもやっておいた方がいいことは?
年間の取引履歴を保存すること、税金計算ツールで損益を把握すること、そして記録・管理を習慣化することが大切です。申告が不要な年でも、翌年以降や税務調査に備えて準備しておくと安心です。
まとめ:暗号資産の20万円以下の税金
- 暗号資産の利益は「雑所得」として課税対象
- 給与所得者は利益が20万円以下なら原則として確定申告不要
- 個人事業主や副業収入がある人は金額に関係なく申告が必要
- 確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある
- 税務署は取引情報を把握しているため、無申告には注意
- 年間取引履歴の保存・損益計算ツールの活用が安心
暗号資産は少額の取引でも税金が発生する可能性があります。とくに副業やフリーランスの方は、申告の有無をしっかり確認することが大切です。
「今年は大丈夫」と思わず、記録や損益のチェックを習慣化して、将来の税務トラブルを防ぎましょう。



暗号資産の確定申告が不安な方は、税理士に無料相談してみるのもおすすめです。また、利益計算に便利な「Gtax」などのツールも活用してみましょう。
